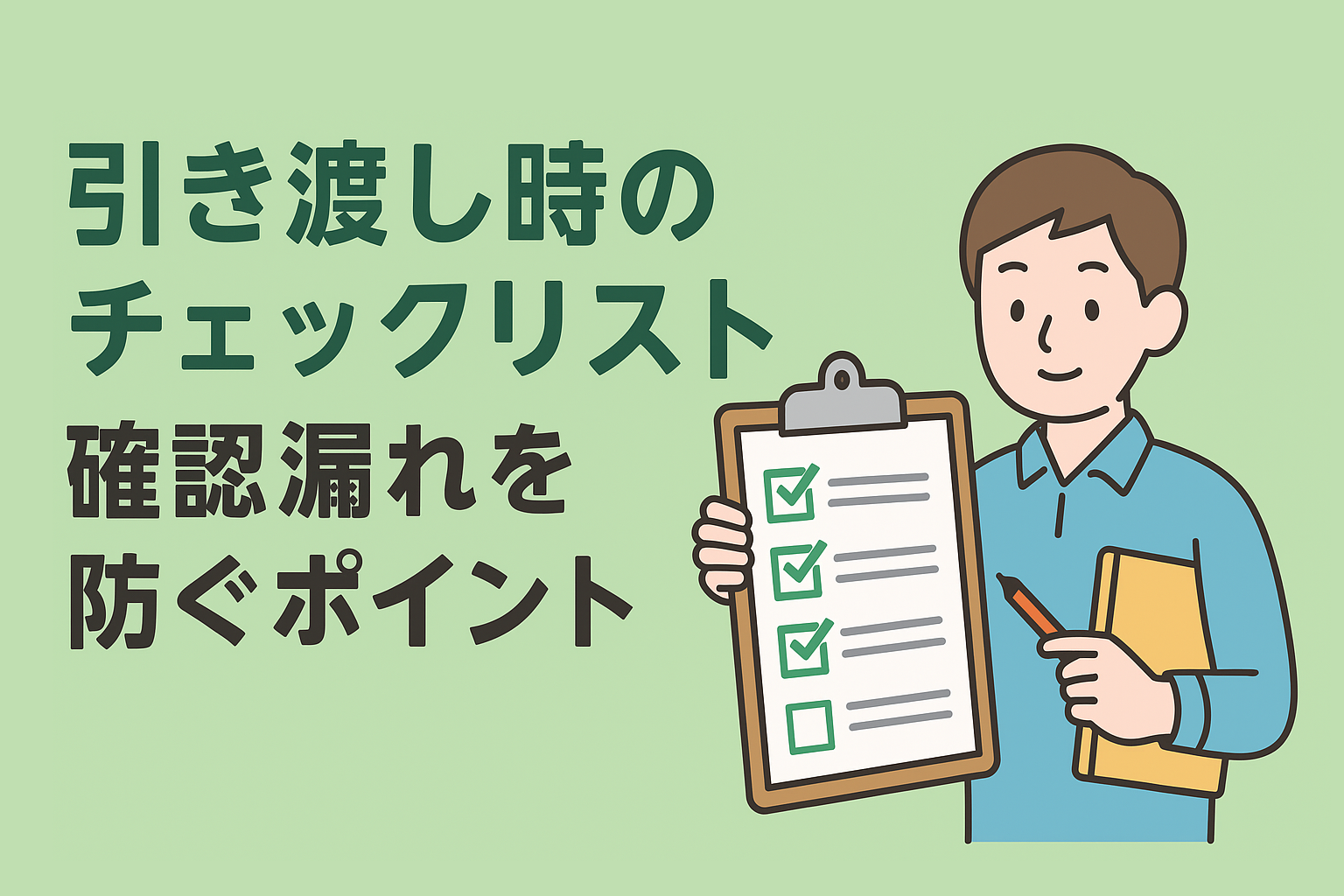注文住宅を建てる際、「実際の工事はどんな流れで進むのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 間取りや設備の打ち合わせが終わったあと、いよいよ現場での建築工事が始まりますが、その過程には多くの工程と専門的な作業が含まれます。 工事の全体像を理解しておくことで、進捗確認や現場チェックがしやすくなり、家づくりの安心感にもつながります。
この記事では、地鎮祭から引き渡しまでの主要な工事工程について、順を追ってわかりやすく解説します。
着工前の準備
地鎮祭(じちんさい)
工事の無事と安全を祈願する神事です。施工会社が神主の手配や供物の準備を行ってくれることが多く、施主は家族とともに参加します。 土地の四隅に青竹を立てて縄を張り、その中央で儀式を行います。 この儀式を行うことで、土地の神様に敬意を表し、工事中のトラブル回避や家族の繁栄を祈願します。
近隣への挨拶回り
着工前に近隣住民への挨拶を済ませておくことで、工事中の騒音や車両出入りによるトラブルを防ぎやすくなります。 粗品(タオルや洗剤など)を持参し、工事期間や工事内容を簡潔に説明しておくとよいでしょう。
仮設工事
・仮囲いで敷地を囲い、関係者以外の立ち入りを防止します。
・仮設トイレや手洗い場を設置し、作業環境を整えます。
・水道・電気・排水などの仮設インフラを引き込み、工事中に必要な設備を確保します。
基礎工事
地盤改良(必要な場合)
建物の重さを支えるには、地盤の強さが重要です。地盤調査の結果によっては、地盤を補強する必要があります。 柱状改良(コンクリート杭を地中に打ち込む)、表層改良(セメント系材料を地表に混合)などの方法があります。
根切り・砕石敷き
基礎の形に合わせて地面を掘削し(根切り)、その上に砕石を敷き詰めて転圧します。 この工程により、基礎下の地盤を安定させ、コンクリートの沈下やひび割れを防ぎます。
捨てコンクリート
砕石の上に薄くコンクリートを打設します。この層は構造的な意味はなく、型枠や鉄筋を正確に配置するための基準となる「墨出し」のために施工されます。
配筋(鉄筋組み)
基礎に強度を持たせるため、鉄筋を格子状に組み立てていきます。 設計図通りに鉄筋が配置されているかを確認する「配筋検査」もこの段階で行われ、合格しないと次の工程に進めません。
コンクリート打設
型枠の中にコンクリートを流し込みます。振動機(バイブレーター)で気泡を抜き、密実に仕上げることが重要です。 打設後は数日間の養生期間を設け、コンクリートの強度がしっかり発現するまで乾燥させます。
上棟(建て方)
土台敷き
基礎の上に土台となる木材を固定し、その上に床下断熱材や合板を施工します。 シロアリ対策として、基礎パッキンや防蟻処理もこの段階で施されます。
柱・梁の建て込み
クレーン車などを使って柱・梁を順番に組み立てていきます。構造体の骨組みが立ち上がることで、建物の形が見えるようになります。 施工スピードが速いため、数日で一気に上棟まで進むこともあります。
上棟(じょうとう)
建物の最上部の棟木を納める工程です。棟木(屋根の一番高い部材)を設置し、建物の構造が完成したことを祝います。 「上棟式」として、工事関係者への感謝を込めた小規模な式を行うこともあります。
屋根・外壁工事
屋根工事
屋根の下地(野地板)を敷いた後、防水シート(ルーフィング)を施工し、瓦や金属板などの屋根材を取り付けます。 防水性能と耐風性能を両立させるため、施工精度が重要な工程です。
外壁下地・防水処理
構造用合板(耐力面材)を外壁に貼り、その上に透湿防水シートを施工して雨水の浸入を防ぎます。 さらに通気層を設けることで、壁内の湿気を排出しやすくなります。
サッシ・玄関ドアの取り付け
サッシや玄関ドアを取り付け、防水テープやシーリング材で防水処理を行います。 窓まわりの防水処理は、雨漏りを防ぐために非常に重要です。
内部工事
配線・配管工事
壁や天井内部に電気の配線、給排水の配管、ガス管などを通します。 コンセントやスイッチの位置はこの段階で確定するため、設計段階での計画が活きてきます。
断熱材施工
グラスウールや吹き付け断熱などを使って、壁・天井・床に断熱材を施工します。 断熱性能の高低は、快適性や光熱費に直結するため、丁寧な施工が求められます。
石膏ボード張り
配線・断熱材の施工が完了したら、石膏ボードを張って内壁の下地を仕上げます。 この段階で部屋の輪郭がはっきりし、空間の広さも実感できるようになります。
内装仕上げ・設備工事
床材・壁紙・建具の施工
フローリングやクッションフロアを施工し、壁・天井にはクロスを貼ります。 建具(室内ドア・収納扉など)も同時に取り付けられ、住宅らしさが一気に増します。
キッチン・トイレ・浴室などの設置
水回り設備を搬入・設置し、電気・水道と接続します。 換気扇や照明器具、エアコンの先行配管なども同時に行われます。
竣工・引き渡し
完了検査
行政または検査機関による「完了検査」を受け、法令に適合していることを確認します。 合格すれば「検査済証」が交付され、登記や融資の手続きにも必要となります。
施主検査
施主が建物内部をチェックし、傷や不具合がないかを確認します。 不備が見つかった場合は、引き渡し前に手直しを依頼します。
手直し・清掃
クロスの隙間、塗装ムラなどの手直しを行い、ハウスクリーニングによって建物をきれいな状態に整えます。
引き渡し
玄関鍵、図面一式、保証書、各設備の取り扱い説明書などを受け取ります。 いよいよ新居での暮らしがスタートします。
まとめ
家づくりの工事工程は、「基礎」から「完成」まで多くの専門的なステップを経て進行していきます。 それぞれの工程には品質確保のポイントがあり、進行中の現場確認や施工会社とのコミュニケーションも重要です。
とくに「基礎配筋」「断熱材」「内装仕上げ」など、見えなくなる部分は後から修正が難しいため、早めに確認しておくと安心です。
現場を理解することは、より納得のいく家づくりへの第一歩。住まい手として主体的に関わりながら、理想のマイホームを形にしていきましょう。