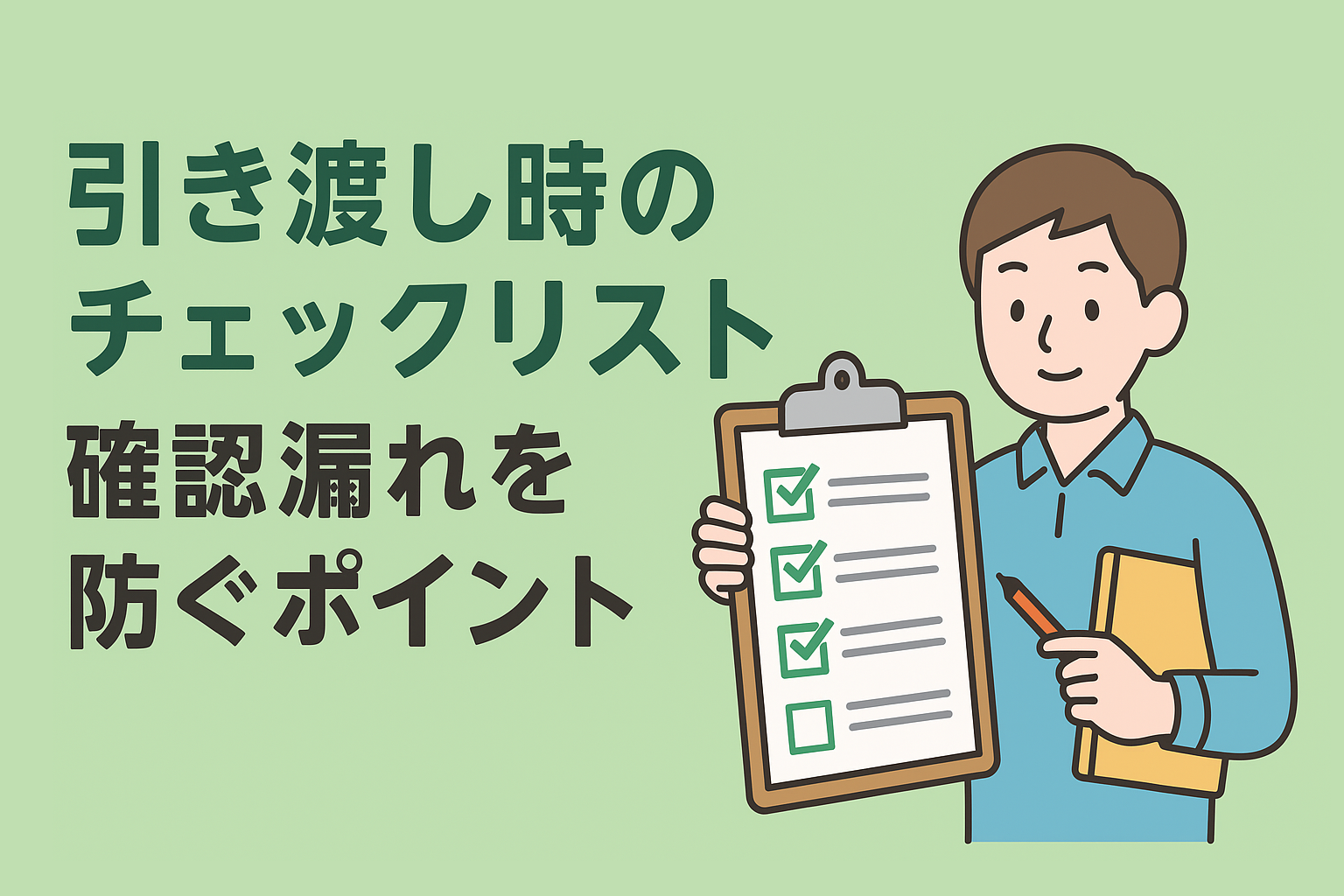住宅は多くの人にとって人生最大の買い物です。完成後も長く安心して暮らすためには、万が一の不具合やトラブルが発生したときの「保証制度」が欠かせません。とくに、新築住宅には法律で義務づけられている保証があり、住宅購入者にとって大切な知識です。
この記事では、新築住宅に適用される「瑕疵担保責任」と、それに基づく「10年保証制度」の内容について解説します。
瑕疵担保責任とは 住宅の欠陥に対する責任
「瑕疵(かし)」とは、建物の構造や性能に関する“欠陥”のことを指します。たとえば、壁にひび割れがあったり、基礎部分に水漏れがあるようなケースが該当します。
新築住宅の場合、建物の売主(施工会社や建売業者など)には、引き渡しから一定期間、このような瑕疵に対して補修などを行う責任があります。これが「瑕疵担保責任」です。
以前は、売主が独自に責任を負っていましたが、トラブルが相次いだことから、2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行され、瑕疵担保責任が制度として明文化されました。
10年保証の内容 どこまで保証されるのか
品確法では、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に対して、最低10年間の保証が義務付けられています。
具体的には以下のような箇所が対象です。
- 構造耐力上主要な部分
基礎・柱・梁・屋根など、建物の強度に関わる部分。 - 雨水の侵入を防止する部分
屋根や外壁、開口部(サッシなど)など、雨漏りを防ぐ部分。
この保証制度により、施工不良や設計ミスなどが原因で不具合が発生した場合、売主や施工業者が無償で修理を行うことが義務づけられています。
住宅瑕疵担保履行法 保険または供託で担保
品確法とセットで施行されているのが、2009年から始まった「住宅瑕疵担保履行法」です。この法律により、売主は保証責任を果たすための資力を、以下のいずれかで担保する必要があります。
住宅瑕疵担保責任保険への加入
保険法人(例:住宅あんしん保証、ハウスプラス住宅保証など)により、保証対象の不具合に保険金が支払われます。施工業者が倒産しても、購入者が保険会社に直接請求できます。
供託金の供託
保険の代わりに、一定の資金を供託しておく方法です。中小規模の建設業者では保険加入が一般的です。
保証の範囲外になるケースもある
10年保証とはいえ、すべての不具合が保証対象になるわけではありません。以下のような場合には、保証対象外とされる可能性があります。
- 自然災害による損傷(地震・台風など)
- 入居後の過失や不適切な使用
- 経年劣化によるもの(クロスの変色やドアのきしみなど)
また、構造や防水以外の部分(内装や設備など)については、業者によって独自の保証期間が設定されていることが多く、通常は1~2年が目安とされています。
長期優良住宅などの追加保証制度
「長期優良住宅」や「住宅性能表示制度」を利用した場合は、さらに手厚い保証やメンテナンス計画が付帯されることもあります。認定を受けた住宅は、一定基準を満たしており、長期間にわたって性能を維持することが想定されています。
保証制度の手厚さを比較検討することは、住宅選びにおける大切な視点のひとつです。
まとめ 保証内容を事前に確認して安心な家づくりを
住宅の保証制度は、家づくりの完成後も安心して暮らすための重要な仕組みです。とくに「10年保証」の対象範囲や、瑕疵担保責任保険の有無は、契約前にしっかり確認しておくのがよいと思います。
保証の範囲外になるケースや、追加の保証制度の有無についても理解しておくことで、万が一のトラブルにも冷静に対応できるはずです。長く安心して住める家を実現するためにも、制度の内容をきちんと把握しておきましょう。