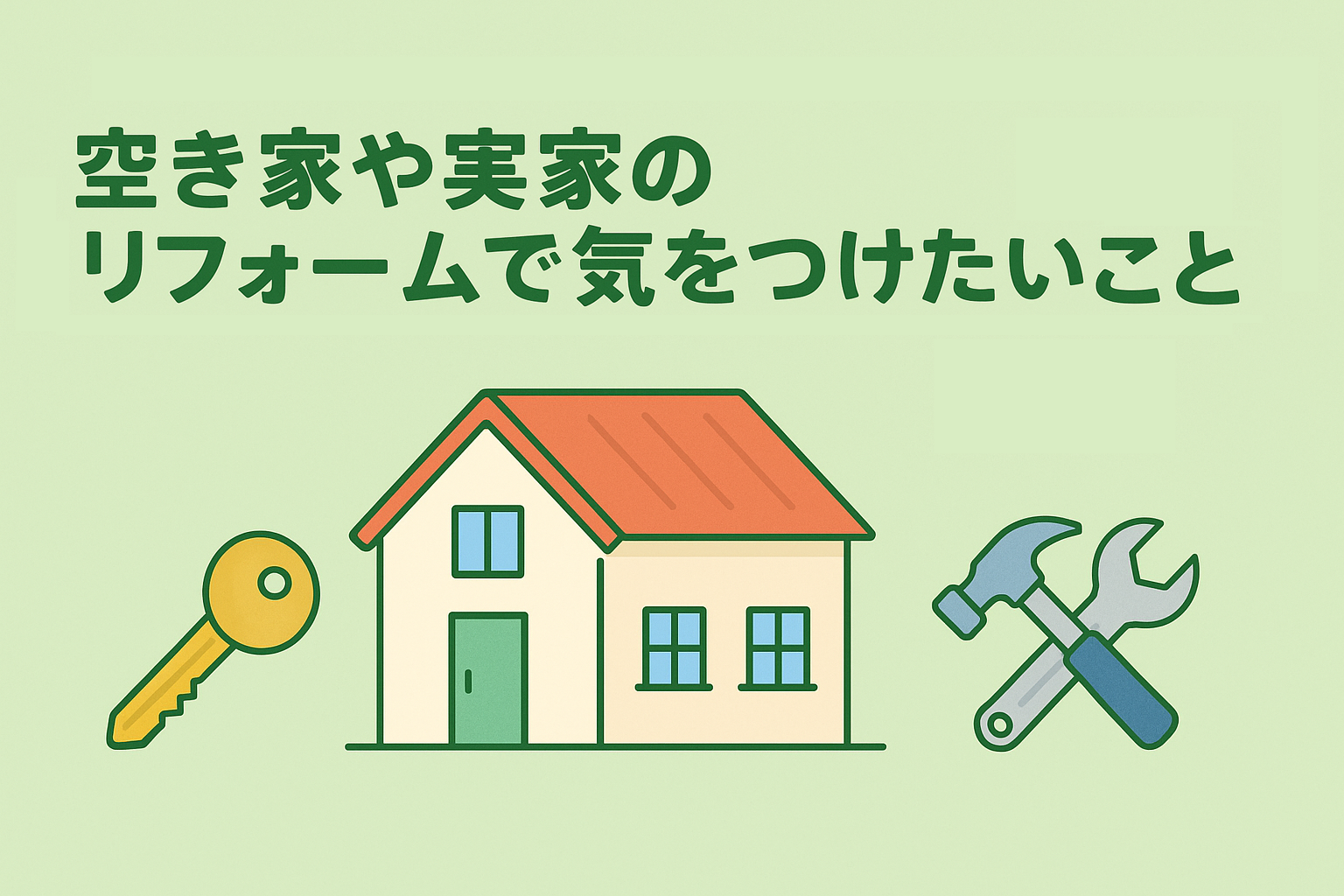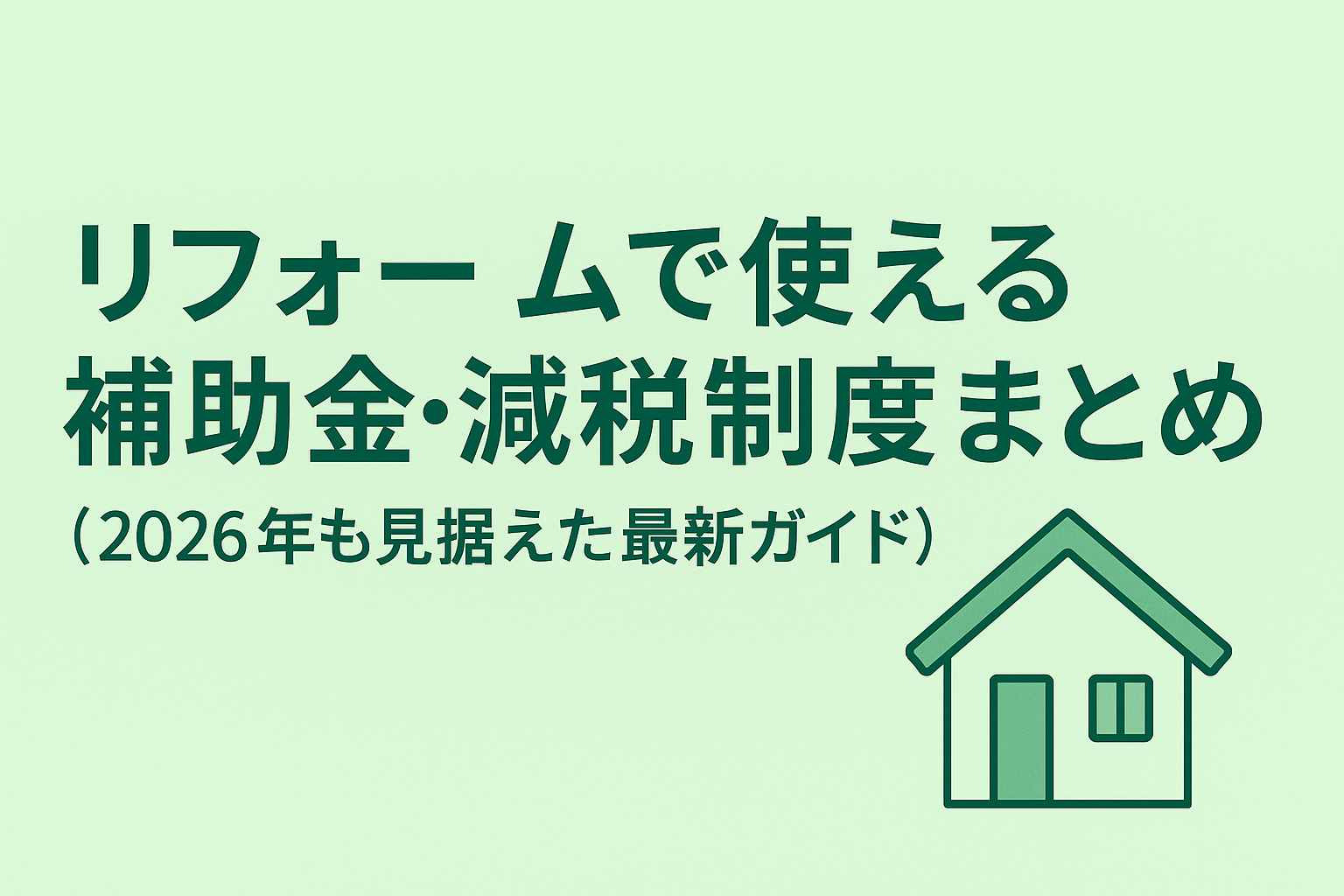少子高齢化が進む中で、親の家を相続したり、長年使われていない実家をどうするかという悩みも増えていると言われています。空き家を放置すると老朽化や倒壊のリスクが高まるだけでなく、固定資産税や防犯面での負担も生じます。ここでは、空き家・実家をリフォームして活用する際に気をつけたいポイントと、活用の選択肢を整理してみました。
空き家を放置すると起こるリスク
老朽化と修繕費の増加
建物は使わなくても劣化します。雨漏りや配管の腐食、シロアリ被害などは放置するほど修繕費がかさむ傾向があります。特に木造住宅の場合、築20年以上経つと屋根や外壁、給排水設備の劣化が顕著になることが多く、早めの点検が欠かせません。
固定資産税や管理費の負担
誰も住んでいなくても、固定資産税は発生します。特定空家等に指定されると、住宅用地特例が外れ、税負担が6倍になることもあります。また、草刈りや通風・通水などの維持管理を業者に依頼する場合、年間で数万円のコストがかかります。
防犯・近隣トラブル
空き家は不審者の侵入や火災のリスクが高く、近隣住民から苦情が出るケースもあります。市区町村によっては空き家の巡回や管理指導を行っていますが、所有者が主体的に対処することが基本です。
リフォーム前に確認しておきたいこと
建物の構造・老朽化の程度を調べる
まずは専門業者や建築士による「住宅診断(インスペクション)」を受けることになります。基礎や屋根、耐震性、配管、断熱などをチェックし、修繕が必要な箇所と再利用できる部分を把握します。
住宅診断(インスペクション)で確認される主な項目
インスペクションは、専門の建築士が建物の状態を第三者として評価する調査です。空き家や築年数の経った実家では、表面からはわからない劣化が進んでいることも多いため、リフォーム内容の優先順位を決めるうえで役立ちます。
構造部分(基礎・柱・梁など)
- 基礎のひび割れ、沈み込み、鉄筋の露出
- 柱・梁の腐食、シロアリ被害、傾きの有無
- 耐震性能が現行基準に対してどの程度不足しているか
屋根・外壁
- 屋根材や瓦のズレ、破損、雨漏り兆候
- 外壁のひび割れ、塗膜の劣化、シーリングの破断
- 防水シートや下地材の劣化状況(必要に応じて開口調査)
給排水・設備関係
- 給水管・排水管の錆び、漏水、耐用年数
- 電気設備(分電盤、アース、古い配線)の安全性
- ガス設備・給湯器の劣化や交換時期の目安
室内・断熱性能
- 床のたわみ、フローリングの浮き、壁のカビ・結露
- 窓周りの気密性・断熱性、サッシの劣化状況
- 天井裏や床下の断熱材の有無・劣化状態
敷地・外構まわり
- 擁壁のひび割れ、排水不良、境界の確認
- 地盤沈下の有無、シロアリの侵入経路になりやすい部分
- 雨水・汚水の排水経路の詰まりや逆流のリスク
調査後の報告書
調査結果は「住宅診断報告書」としてまとめられ、劣化箇所・改修の緊急度・概算費用の目安などが整理されます。これにより、
- どこから手をつけるべきか(優先順位)
- どの程度の工事規模になりそうか
- リフォームか建て替えか
といった判断がしやすくなります。
住宅診断(インスペクション)の費用目安
インスペクションは建物の状態を客観的に把握するための調査で、費用は調査内容や建物の規模によって変わります。空き家や築年数の経った実家では劣化が見えにくい部分が多いため、事前におおよその費用感を知っておくと計画が立てやすくなります。
基本診断(一次インスペクション)
- 戸建て(延床100㎡前後):約5万円〜7万円
- マンション(専有部):約3万円〜6万円
外観や屋根、床下、給排水、電気設備などを中心に、目視で劣化状況を確認するもっとも一般的な診断です。
詳細診断(二次インスペクション)
- 戸建て:約8万円〜15万円
- マンション:約6万円〜10万円
サーモカメラや水平器などの機材を使い、断熱や傾き、雨漏りの兆候まで詳しく調査します。リフォームの優先順位を決める材料として役立ちます。
追加オプションの目安
- 床下侵入調査:+1〜3万円
- 屋根ドローン点検:+1〜2万円
- シロアリ調査:+1〜2万円
- アスベスト簡易検査:1〜3万円
- 耐震診断(木造):5〜15万円
補助金が利用できる場合もある
自治体によっては、インスペクション費用の一部を助成しています。空き家バンク登録で補助が出る地域や、耐震診断と組み合わせて支援があるケースもあります。「市区町村名 + インスペクション補助金」で検索すると、最新の制度が見つかりやすくなります。
法規制や再建築の可否を確認する
接道条件を満たしていない「再建築不可物件」や、都市計画区域・用途地域の制限がある場合、リフォーム内容に制約が生じます。建築確認が必要な工事では、必ず自治体の建築指導課などに相談しておくと安心です。
リフォーム費用と資金計画を立てる
古い住宅では、表面の内装工事だけでなく、耐震補強や配管・電気設備の更新が必要になる場合があります。構造や延床面積にもよりますが、フルリフォームでは500万円〜1,000万円を超えることもあります。補助金や税制優遇の利用を検討して、無理のない資金計画を立てるのがよいと思います。
空き家・実家リフォームの補助金・支援制度
国の制度
2025年度以降は、国交省の「住宅省エネ2025キャンペーン」や「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が中心的な支援制度となっています。断熱改修や耐震補強、バリアフリー改修など、一定の性能向上を伴うリフォームが対象です。
自治体の補助金
各自治体では、空き家活用を促進するための独自の補助制度を設けています。たとえば、空き家バンク登録物件のリフォーム費用を一部助成したり、移住者向けリフォーム支援を実施する自治体もあります。
「〇〇市 空き家 補助金」などで検索すると、最新情報を確認できます。
税制優遇
耐震・省エネ・バリアフリーなどの改修を行う場合、「リフォーム促進税制」や「住宅ローン減税(増改築)」が利用できる場合があります。所得税や固定資産税の軽減が受けられる可能性があるため、事前に税務署や施工業者に確認しておくのがよいと思います。
リフォーム後の活用方法
自分や家族が住む
将来的にUターン・セカンドライフ用の住宅として活用する方法です。断熱改修や段差解消などを行えば、快適で安全な住まいに生まれ変わります。二世帯住宅への改修も選択肢のひとつです。
賃貸・民泊として貸し出す
地域によっては古民家をリノベーションして賃貸住宅や民泊にする動きも増えています。リフォーム時に防火・避難経路・設備基準などを満たす必要があるため、用途変更を伴う場合は行政確認が欠かせません。
店舗・オフィス・サロンとして再利用
住宅をカフェや雑貨店、アトリエ、オフィスとして活用する例もあります。立地条件によっては、住宅地でも「兼用住宅」として一部の事業用途が可能な場合があります。
解体・建て替えを含めた再活用
老朽化が進み、構造的にリフォームが難しい場合は、解体・新築という選択もあります。更地にして駐車場として貸す、または新たに戸建てや賃貸住宅を建てるなど、土地活用の選択肢も検討してみるとよいと思います。
まとめ
空き家や実家を放置すると、維持コストや近隣トラブルのリスクが高まります。建物の現状を正しく把握し、補助金や制度を活用しながらリフォームや活用方法を考えることが必要になってきます。
所有者不明化を防ぐためにも、相続登記や管理契約などの手続きも早めに進めておくと安心です。