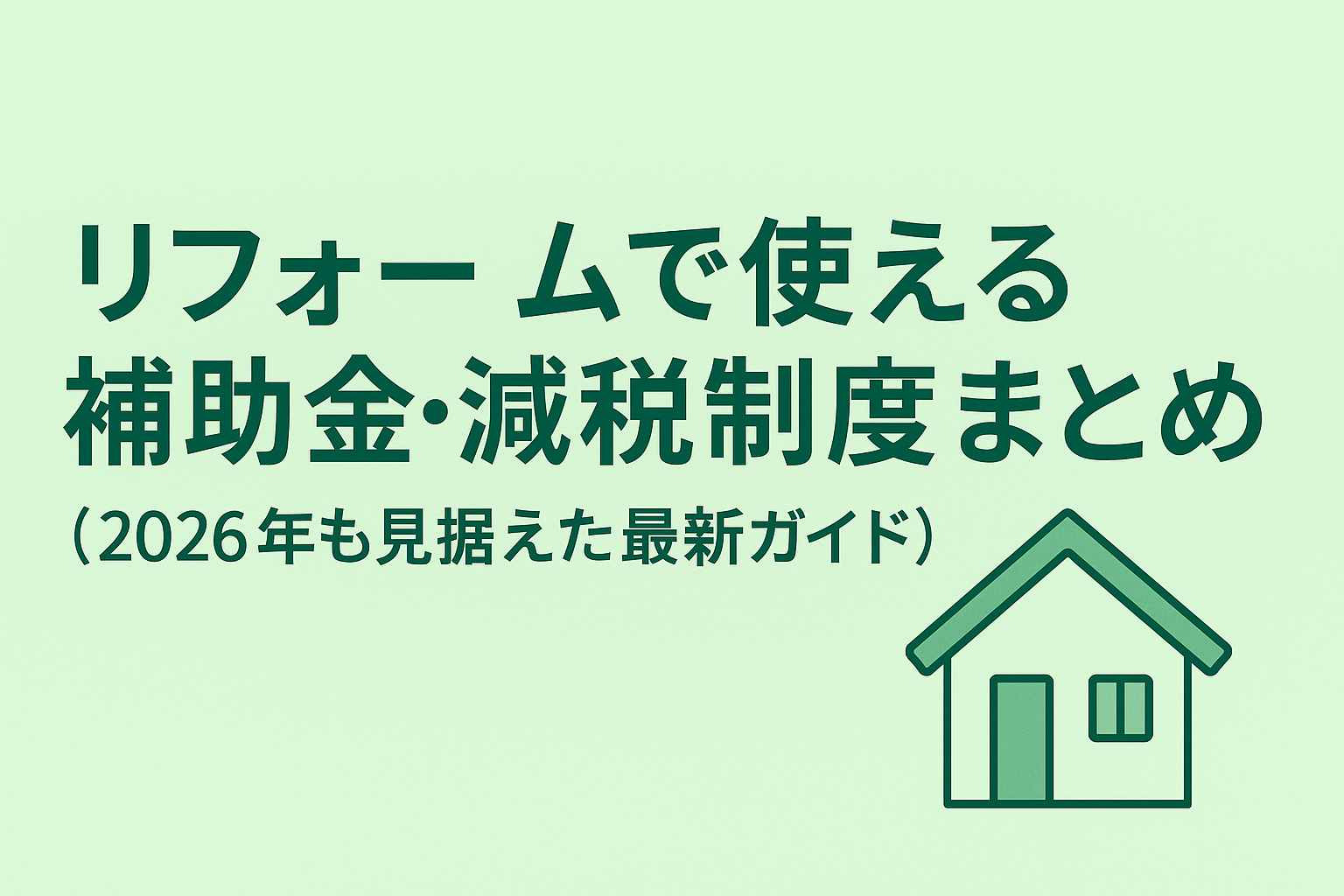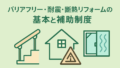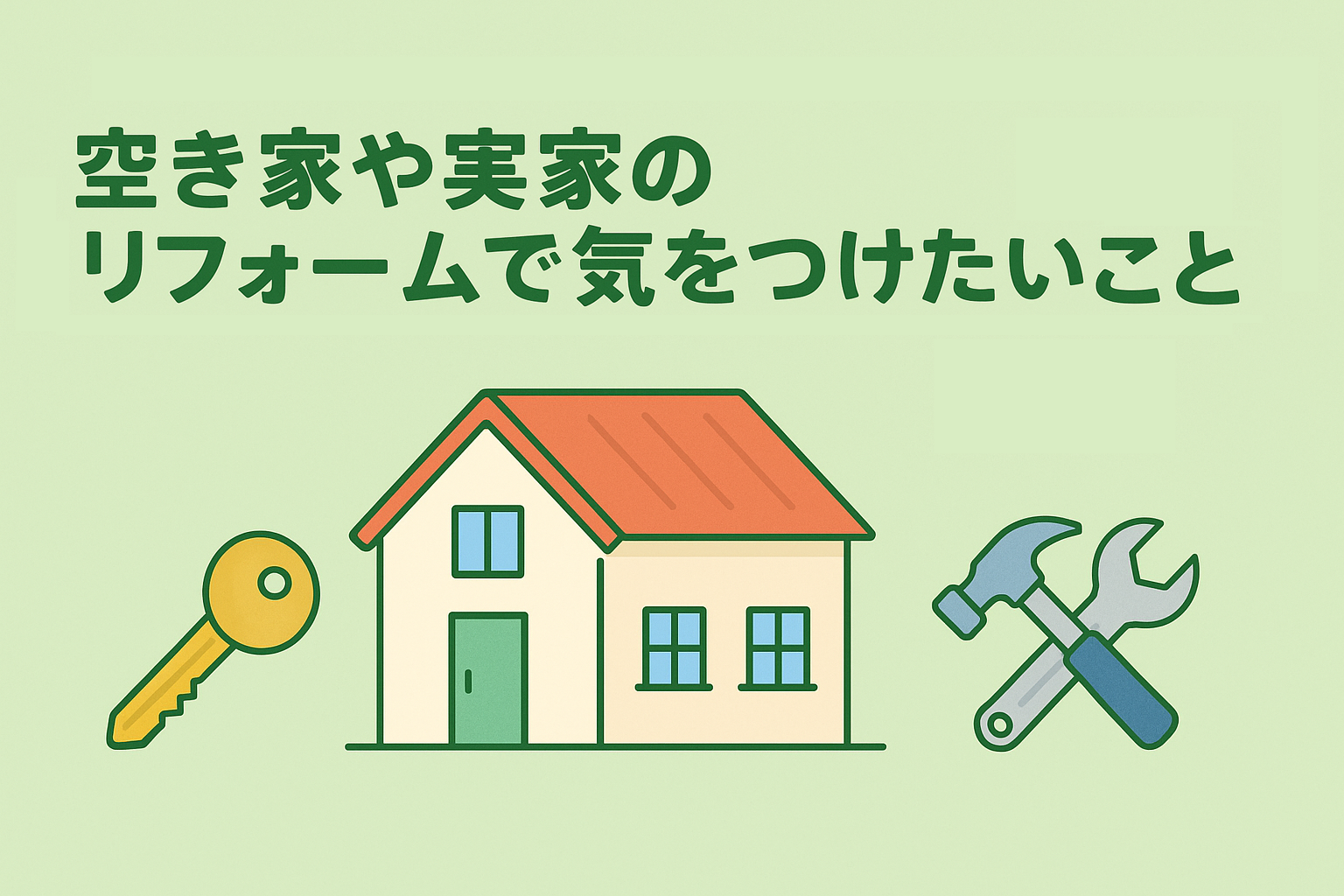省エネ・快適性・安全性を高めるリフォームは、国や自治体の支援を上手に組み合わせることで自己負担を抑えやすくなります。
ここでは、2025年時点で利用できる制度のうち、今後(2026年以降)も注目したい枠組みを整理しました。金額や要件は事業ごとに異なるため、正式な申請前に必ず公式情報で最新状況をご確認ください。
住宅省エネ2025キャンペーン(リフォーム向けの4事業)
国交省・経産省・環境省の3省連携による省エネリフォーム支援です。予算消化状況により受付終了のタイミングが変わるため、早めの確認が安心です。各事業は条件により組み合わせ可能です。
① 子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)
- 対象: 既存住宅の省エネ改修(開口部・躯体等)、子育て対応改修 など
- 補助額目安: 最大60万円/戸(工事内容・世帯要件により異なる)
- ポイント: 申請は登録事業者経由。受付枠に達すると終了。
公式サイト: 子育てグリーン住宅支援事業
② 先進的窓リノベ2025事業
- 対象: 高い断熱性能を有する製品による窓の改修(交換・内窓・ガラス等)
- 補助額目安: 最大200万円/戸(住宅規模・窓の仕様などで変動)
- ポイント: 開口部の断熱は体感改善と光熱費削減に直結。優先度を上げやすい分野。
公式サイト: 先進的窓リノベ2025
③ 給湯省エネ2025事業
- 対象: 高効率給湯器(エコキュート/ハイブリッド 等)の設置
- 補助額目安: 最大20万円/戸
- ポイント: 光熱費インパクトが大きい設備分野。製品登録・性能要件の確認が必須。
公式サイト: 給湯省エネ2025
④ 賃貸集合給湯省エネ2025事業
- 対象: 賃貸集合住宅の住戸で省エネ型給湯器(エコジョーズ等)に交換
- 補助額目安: 最大10万円/戸
- ポイント: 賃貸オーナー向け。住戸ごとの交換で効果が積み上がる。
公式サイト: 賃貸集合給湯省エネ2025
長期優良住宅化リフォーム推進事業(令和7年度)
- 対象: 劣化対策・耐震性・省エネ性など所定基準を満たす性能向上リフォーム
- 補助額例: 認定長期優良住宅型 160万円/戸、評価基準型 80万円/戸 など
- ポイント: インスペクションや履歴・維持保全計画の作成が必須。長期視点の改修に最適。
事業者公表: 令和7年度 事業者の公表ページ
耐震改修・高齢者向け改修・自治体独自の助成
耐震改修(国・自治体連携)
- 対象: 耐震診断・補強設計、壁や基礎の補強、屋根の軽量化 など
- ポイント: 自治体により上限・補助率が異なる(例: 診断費助成、改修費の一定割合を補助等)。
出典: 国交省「災害に強い住宅・建築物の整備(住宅・建築物耐震改修事業)」
制度概要/耐震化の現状と目標
介護保険の住宅改修(バリアフリー)
- 対象工事: 手すり設置、段差解消、滑りにくい床材、扉の引き戸化、浴室・トイレの改修 など
- 給付: 原則 上限20万円(9割給付=最大18万円)。区分が3段階上がった場合や転居時は再度上限設定。
- 流れ: 事前申請→工事→支給申請。ケアマネ等の理由書・写真・見積 等が必要。
出典:
厚生労働省「介護保険における住宅改修」(手続・書類)
厚生労働省資料(住宅改修の支給限度基準額 20万円等)
自治体独自の補助
省エネ・耐震・バリアフリー・空き家活用 等の独自助成が多数あります。国費充当分は他制度と併用不可のことがあるため、併用可否を確認してください。
自治体制度の横断検索:
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「支援制度検索サイト」
減税制度(住宅ローン減税〈増改築〉/リフォーム促進税制)
補助金とあわせて、税制優遇の活用も効果的です。適用は自己申告(確定申告)が必要です。
住宅ローン減税(増改築)
- 10年以上のローンを利用し、一定のリフォームを行った場合に対象。
- 各年末の住宅ローン残高の0.7%を最大10年間控除(適用条件・金額要件あり)。
リフォーム促進税制(投資型・固定資産税減額 等)
- ローン利用の有無に関わらず活用可能。
- 対象メニュー(耐震/バリアフリー/省エネ/三世代同居対応/長期優良住宅化/子育て)のうち、内容に応じて所得税 最大60~80万円控除、固定資産税 1/3~2/3減額など。
- 制度間の併用関係(可否)は公式表で確認可能。
出典: 国交省「リフォームをお考えの消費者の方」
(減税の仕組み・併用表・シミュレーション)
申請の流れと実務ポイント
- 登録事業者経由が基本:
住宅省エネ2025の申請は、原則として登録を受けた施工事業者が行います(事業者検索可)。 - 契約前の要件確認:
対象工事・製品型番・工事金額・着工/完了時期・提出書類など、事前確認が重要です。 - 補助金と減税のセット設計:
まず補助金の上限と併用可否を押さえ、完了後に減税申告(必要書類の保管・取得)まで見通しておくとスムーズです。 - 自治体枠の早期終了に注意:
交付申請は「上限に達し次第終了」が一般的。募集開始時期の把握と書類準備が鍵になります。