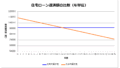マイホームを建てたいと思ったとき、最も気になるのが「自分たちの年収で、どれくらいの家を建てられるのか」という点です。
この記事では、年収ごとに家づくりの予算の目安をシミュレーションしながら、無理のない資金計画の立て方を紹介していきます。
住宅ローンの借入可能額の目安や、総予算の組み立て方を理解することで、現実的なプランが見えてきます。
年収別の借入可能額と総予算の目安
住宅ローンを組む際、一般的に「年収の25〜30%以内」に年間返済額を抑えるのが理想とされています。
以下は、年収ごとの借入可能額の目安です(返済期間35年、金利1.0%想定)。
| 年収 | 借入可能額の目安 | 総予算(自己資金含む) |
| 400万円 | 約2,500万円 | 約2,700〜3,000万円 |
| 500万円 | 約3,100万円 | 約3,300〜3,600万円 |
| 600万円 | 約3,800万円 | 約4,000〜4,300万円 |
| 700万円 | 約4,400万円 | 約4,600〜5,000万円 |
| 800万円 | 約5,000万円 | 約5,300〜5,700万円 |
※自己資金は200〜500万円程度を想定。ボーナス返済は考慮していません。
無理のないローン返済のために考えるべきこと
- 「返済比率」は25%以下が安心
- 固定費(車・教育費など)とのバランス
- 子育てや老後のライフイベントを含めた長期的な視点
- 夫婦の収入バランスと共働き継続の可能性
住宅ローンは長期にわたる契約のため、現在の収入だけでなく、将来の変化も見据えた資金計画が求められます。たとえば、子どもの進学や教育費、車の買い替え、転職・退職など、人生のさまざまな変化に備えておきたいところです。
総予算の組み立て方
注文住宅を建てる際には、「土地+建物+諸費用+オプション」のすべてを含めた総額で予算を考えます。
一般的には次のような構成になります:
- 建物本体価格:60〜70%
- 土地代(購入する場合):20〜30%
- 諸費用・付帯工事・オプション:10〜15%
たとえば、年収600万円の家庭が4,000万円の予算を組む場合、建物にかけられる費用は約2,400〜2,800万円となります。
土地・建物以外にかかる費用の具体例
家を建てる際は、建物そのものの費用だけでなく、次のようなさまざまな費用が発生します。
- 登記費用(所有権移転・保存・抵当権設定など)
- 住宅ローンの保証料、手数料、印紙税
- 地盤調査・地盤改良費用
- 給排水工事・外構工事(駐車場・塀など)
- 引っ越し代、仮住まい費用(建て替え時)
- 火災保険・地震保険
- 照明・カーテン・エアコンなどの家具家電
これらはすべて合計で数百万円にのぼることもあり、あらかじめ総予算に組み込んでおくことが重要です。
手元資金はどのくらい残しておくべき?
自己資金をすべて家づくりに使ってしまうと、急な出費に対応できなくなってしまうことも。目安として、生活費の6ヶ月〜1年分程度を手元に残しておくのが安心とされています。
子どもの進学、医療費、車の買い替えなど、将来の出費も考慮しながら、自己資金の一部をあえて残すという判断も大切です。
保険の見直しも忘れずに
住宅ローンを組むと、多くの場合「団体信用生命保険(団信)」に加入することになります。これにより、万一のときには住宅ローンが免除される仕組みになりますが、生命保険との重複が発生することもあります。
家計を見直すタイミングとして、保険の内容も一度見直しておくと、支出の最適化につながります。
家を建てたあとの費用にも備える
新築後も、住まいには定期的な費用がかかります。
- 固定資産税・都市計画税(年数万円〜)
- メンテナンス費用(外壁塗装・給湯器交換など)
- 住宅ローン返済とは別の生活コスト
- 設備の修繕・交換(10〜15年ごとに必要)
家を建てることはゴールではなく、住み続けるためのスタートでもあります。
将来的な維持管理費用も視野に入れ、余裕のある資金計画を心がけておくと安心です。
まとめ:無理のない予算シミュレーションが家づくり成功の鍵
家づくりでは、「背伸びしすぎず、将来も安心できる予算を立てる」ことが大切です。
同じ年収でも、支出のバランスや暮らしの価値観は人それぞれです。
趣味や教育費を重視する家庭、将来の二世帯同居を想定する家庭など、それぞれに合った資金配分を考えていきたいところです。
年収に応じた現実的な資金計画を立てることで、ローン返済の不安を減らし、満足のいく住まいづくりにつながっていきます。
「どこにどれだけかけるか」という優先順位を明確にし、自分たちのライフスタイルに合った家づくりを目指してみてください。